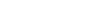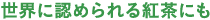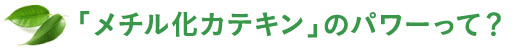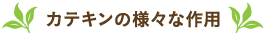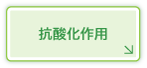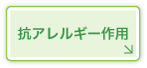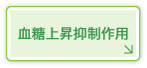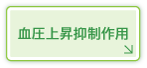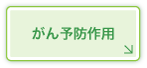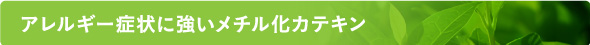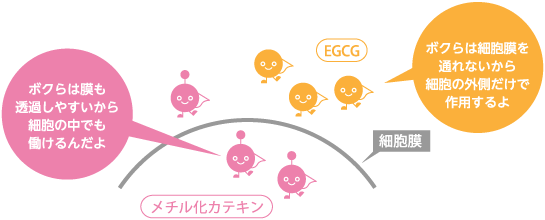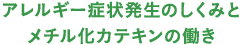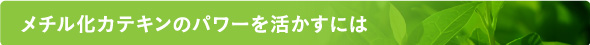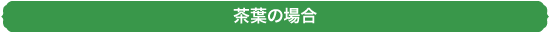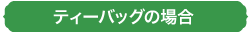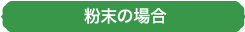教えて、先生!もっと知りたいべにふうき
『生産地から』でご紹介した「べにふうき」は、
なじみのないお茶という方も多いと思いますが、実は抗アレルギー作用が非常に高く、その機能性で注目されている品種なのです。
今回、長年にわたり「べにふうき」の研究にかかわるお茶のエキスパート、山本(前田)万里先生に詳しいお話を聞きました。

「べにふうき」はもともと「紅茶・半発酵茶用」に開発された品種。日本生まれの紅茶「べにほまれ」とダージリン系の「枕Cd86」を交配させ、1965年に誕生しました。ところが、1970年代に紅茶の輸入が自由化され、その影響を受けて品種登録されることなく、忘れ去られた存在になってしまったのです。再び、日の目を見たのは約20年後。烏龍茶ブームを受けて日本で初めての「紅茶・半発酵茶兼用品種」として1993年に命名登録、1995年に品種登録されました。


1999年に、お茶に含まれる成分「メチル化カテキン」が高い抗アレルギー作用を持つことが判明しました。この機能性を活用するため、どのお茶に多く含まれるかを調べた結果、べにふうきの含有量が圧倒的に多いことがわかったのです。しかしながら、もともとは紅茶・半発酵茶用として開発されたお茶。紅茶にするために発酵させるとカテキンが失われてしまいます。そのため、機能性を優先して、緑茶として飲用することになりました。当時は、わずかな面積でしか栽培されていませんでしたが、これを機に栽培面積が増加、現在では「べにふうき緑茶」として鹿児島や静岡を中心に広く栽培されています。
「べにふうき」は緑茶として活用される一方で、現在では国産の紅茶としてもその実力を発揮しています。ロンドンで開催された食品コンテスト「グレード・テイスト・アワード」において、2007年以降4度の金賞を受賞し、紅茶としての実力を世界に認められています。
「べにふうき」に含まれるメチル化カテキンが、抗アレルギー作用を有していることから、その効果や作用メカニズムを科学的に検証して、“ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減する”という機能性表示をパッケージに記載した商品2点(届出番号:A67、A69)が、機能性表示食品として消費者庁に届出・受理されています※。
※2016年3月現在
お茶の中には6〜7種類のカテキンが含まれています。その中で最も含量の多いのがEGCG[(-)エピガロカテキンガレート]と呼ばれるカテキンです。高い抗アレルギー作用を示すメチル化カテキンは、このEGCGが一部メチル化したもの。メチル化することで細胞膜を透過しやすくなり、細胞の中でも活躍が可能になるのです。
アレルギーは花粉などに含まれるアレルギーを起こす物質(アレルゲン)が抗体と反応することで情報が送られ、炎症性物質(ヒスタミンなど)が放出されて、くしゃみや鼻づまり、かゆみなどの症状を起こします。メチル化カテキンは、細胞の外側だけでなく細胞内部の情報伝達経路にも働きかけられるので、より効率的に炎症性物質の放出を抑制できます。


大切なのは、体内にメチル化カテキンがある状態を保つことです。メチル化カテキンを多く含む「べにふうき緑茶」を飲み続けることで、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感軽減の作用を持続することができます。
茶葉・ティーバッグ・粉末ともに90度以上の熱湯で淹れ、必ず冷ましてから飲むようにしてください。また、ほんの少し生姜を加えるとより効果が高くなります。飲みづらい場合は、牛乳を加えて緑茶ラテにするとよいでしょう。
- 茶葉の量:2-3g
- 湯の温度:90度以上
- 湯の量:200ml
- 浸出時間:2分

急須で淹れる以外にも茶葉をだしパックに入れて、やかんで5分間煮るとメチル化カテキンを効率的に摂取できます。

- 湯の温度:90度以上
- 湯の量:150〜180ml
- 浸出時間:2分間振る

- 粉末の量:2g
- 湯の温度:90度以上
- 湯の量:150ml〜180ml
- 浸出時間:30秒撹拌

お話を聞いた人
農学博士 山本(前田)万里 先生
食料・農業・農村に関する 研究開発を行う「独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)」で機能性の研究を担当している。茶の機能性研究によりメチル化カテキンの抗アレルギー作用、べにふうきの機能性を明らかにした「べにふうき緑茶」研究のパイオニア。様々な茶葉の機能性を活かした製品開発なども行なっている。