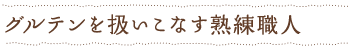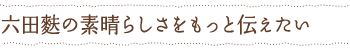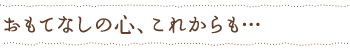【山形発】六田麩:山形県は東根市・六田地区の羽州街道沿いに5つの麩工房が軒を連ねる、通称「六田麩街道」。中でも一番長い歴史を誇るのが創業文久年間の文四郎麩。肉や魚などのたんぱく源が乏しいこの地域で愛される六田麩の魅力を七代目・斎藤幸信さんに伺いました。
中国より伝来した麩づくりの技術は、京都や金沢をはじめ、様々な地域に伝わりました。宿場町であった東根市の六田地区に伝わったのは江戸末期。肉や魚がなかなか手に入らない内陸部で、おもてなし料理のメインとなるべく、こだわったのは食感と風味。稀に見るグルテン含有量で煮崩れず、出汁をたっぷり含んだ食感はまるで肉のようです。良質なたんぱく源である上に日持ちするため、この地域には欠かせない食材となりました。
六田麩街道がある山形県の東根市といえば、さくらんぼの王様的存在「佐藤錦」の名産地として有名ですが、もともとは紅花や葉煙草の栽培が盛んで、畑の連作障害を避けるために裏作で小麦を栽培していました。加えて奥羽山系の清らかな伏流水があちこちから湧き出て、そのおいしさは参勤交代で立ち寄ったお殿様のお墨付きを得たそうです。小麦と水が潤沢という、麩づくりの条件を満たしたこの地に、上方よりやってきた職人が技術を伝えたのは1800年代初頭のこと。それ以降、宿場町として栄えた六田では、趣向を凝らした麩料理で旅人をもてなし、各地で評判になりました。そのうまさと滋養で長旅の疲れも癒されたに違いありません。
文四郎麩の創業は文久年間。六田に伝わる車麩を一貫して作り続け、150年余りの歴史を誇ります。ひと口に車麩といっても地域によって作り方はさまざま。六田麩のうまさの秘密は「グルテン」の含有量にあります。グルテンは小麦粉を水で洗って澱粉質を落としたたんぱく質の塊で、100kgの強力粉から50kgしかとれません。通常の車麩はグルテン10につき小麦粉を15ほどを混ぜるのに対し、六田では小麦粉を0.5にまで抑えています。軽やかな焼き上がりと、水で戻した時のつるりとした舌触り、歯を押し返す弾力は、このグルテンの成せる業。小麦粉を清らかな伏流水で磨き抜く、贅沢かつ手間暇かかるこの製法は、時代や取り巻く環境が変わっても譲れないと、次に文四郎の名を継承する七代目・齊藤幸信さんは語ります。

文四郎麩の敷地内に涌き出す「六田水」。参勤交代で訪れた秋田の佐竹藩主にも気に入られ、「佐竹水」と呼ばれたほどの名水。
 100kgの強力粉から50kgしかとれないたんぱく質の塊「グルテン」。コシの強い餅のような生地に、わずかな小麦粉を加えて成形する。
100kgの強力粉から50kgしかとれないたんぱく質の塊「グルテン」。コシの強い餅のような生地に、わずかな小麦粉を加えて成形する。

小麦粉と水で作った生地を金棒に巻き、焼き上げて芯に。その上からグルテン主体の生地をグッと引っ張りながら巻き付けて焼成。

金棒を抜いてホカホカと湯気が上がったまま梁に吊るし、乾燥させた後で様々な大きさに切り分けます。
家庭科や理科の実験で触れたことがある方はご存知でしょうが、グルテンは非常にコシが強く、容易に伸ばすことができません。0.5の小麦粉は、グルテンを扱いやすくするための、いわば潤滑油のような存在なのです。文四郎麩の麩づくりは全て手作業で、巻き付けの工程には熟練の技を要します。この道60年という職人さんの手から金棒へと渡された生地は引きが強く、グルテンとは思えないほどしなやかに伸びて、みるみるうちに巻き取られ、あっという間に焼き釜へと送り出されていきました。その手さばきたるや、まるで水が流れるような滑らかさ。焼き上げた麩は熱いうちに金棒から外して半分に断ち、張り巡らされた梁へと吊るします。工房は立ち上る湯気と芳しい香りに満たされていました。
丹念に焼き上げた麩は一晩乾燥させ、ぶつ切りや輪切りなど、さまざまな大きさに加工します。羽州街道に面した文四郎麩のウィンドウには、大きな巾着袋に詰められた輪切りの車麩が暖簾のように提げられていました。巾着袋に詰める理由を尋ねたところ「この辺りの家庭では、皆さん台所の片隅に吊るして欲しい時に欲しいだけ取り出して使っているんですよ」との回答に納得。内陸部で肉や魚などが手に入りにくい六田では、良質なたんぱく質の塊・麩は貴重な栄養源で、台所の馴染み顔。家族の健康を預かる主婦たちは、井戸端会議で情報交換をしながら料理のレパートリーを増やしていったのでしょう。煮くずれない特長を活かした卵とじや煮物をはじめ、煮含ませた後に揚げ出すなど、調理次第で七変化。出汁をたっぷり吸った麩をギュッと噛みしめると口内に旨味がほとばしり、食感は獣肉に迫るものがあります。
文四郎麩で腕を磨いた職人達が次々と工房を開くと、いつしか六田麩街道と呼ばれるようになりました。昭和初期には100人以上の行商人がおり、県内外で売り歩いたそうです。しかし、8軒あった工房も今や5軒に。全国的に見てもこの20年で半減したといいます。この事態を見かねて動いたのが六代目文四郎さん。伝統料理から創作まで200種以上のレシピを引っさげ、県内の各地で無料の料理教室を開き、麩の素晴らしさを伝え歩きました。その集大成として六代目が開いたのが文四郎麩一角にある「六田ふ懐石料理処 清居」。季節の移ろいを感じさせる麩懐石が口コミで広がり、今では全国各地から噂を聞きつけた人々が訪れます。一方、東根市に働きかけ、小・中学校の学校給食に六田麩が採用されるなど、幼い頃から慣れ親しむ環境づくりにも余念がありません。街を挙げて六田麩を全国にPRする活動も始まり、六代目の地道な働きかけが実を結びつつあります。
現在、通販の登録者数が5万人を数えるまでになった文四郎麩。「200年以上もこの地で愛され続けるには、それなりの理由があるはず。その理由を後世へ伝え続けるためにも、時代に合った提案をしていくのが私の使命です」と七代目。伝統は守りながらも、新たなレシピや半調理した商品を提案することで、もっと気軽に楽しんで欲しいと語ります。店頭では麩料理の試食を切らすことなく供し、レシピの数々を綴ったリーフレットを惜しみなく配っていました。すべては六田麩の「おいしさ」に触れて「感動」してもらいたいという思いから。宿場町・六田のおもてなしの心は、七代にわたって脈々と受け継がれているようです。

巾着袋に詰められ、ウィンドウに吊るされた六田麩。「実家の台所にもあったわ」と、帰郷中らしきご夫人から懐かしむ声が。

文四郎麩の店舗で供される定番料理「毎日つくる麩の煮物」。旨味をたっぷり含んだ麩の味わいが、郷愁を誘います。
※掲載の内容は、2013年11月現在のものです。